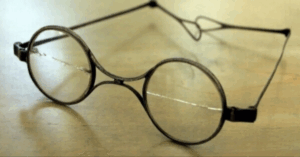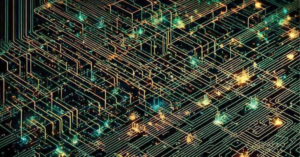【設備設計】書店と設備設計の共通店
実家の近くに自分が小学生の頃なので約30年以上前から続いている町の書店がある。先日、車で母とそのそばを通った時、ぼそっと、この書店は無くならないでほしいなと言った。

20年ほど前、その書店の近くに大きめの書店が出来たことがある。そのお店は出来たときは流行っていたが、次第にお客さんが少なくなって閉店してしまった。
その書店に行くと、通路に開きかけの段ボールがあって通路を塞いでいたり、戸棚の整理があまりできていなくて本が探しにくかった記憶がある。そして、次第にいかがわしい本が増えていき、出入りする客層が悪くなり、家族で行く人が減っていった結果なんだと思う。
今でも続いている方の本屋さんは、派手さはないが実用書があったり、CDや文房具を扱ったりと、その時々でその地域の人々が求めている商品を扱っている事が今でも存続できている理由だと思う。
設備設計も書店も、製品そのものを作り出すという仕事ではないけれど、その建物に合う商品を選んで、きれいに配置して、価値を提供するという点では共通店があると思う。
何となく行きたくなる、近所にあったらいいなと思う書店の様に、1つ1つの商品の選択や配置、図面の見やすさなど、小さな事の積み重ねが商売を続けるには重要なんだなと思う。
母が言った無くならないでほしい書店の様に、地域や社会から必要とされる会社にしていきたいなと思った。